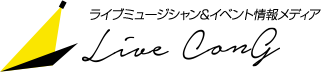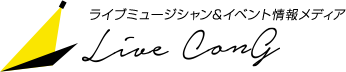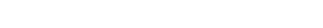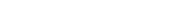Syrup 16gのコード進⾏から⾒たすごさ
画像出典:https://youtu.be/FyD0jRsAqNk
1996年の結成から2008年の解散まで、激情と焦燥をまき散らすような世界観をくり広げたスリーピースバンド、Syrup 16g。
不器用でひねくれた人間の内面性にどこまでも迫り、息の詰まるような苦しさを吐き出す歌詞、そしてそれに輪郭を与えるゴリゴリのオルタナティブロックサウンドで、2000年前後の邦楽ロックシーンを代表するバンドのひとつとして知られています。
そんなSyrup 16gの音楽性は「鬱ロック」と呼ばれるジャンルとして解散後も長く愛されて、次世代のバンドたちにもその精神が受け継がれてきました。
まさに、邦楽ロック史に残る伝説的なバンドといえます。
さらに、2014年には再結成されて現在進行形で話題を集めているSyrup 16g。
今回は、彼らの楽曲の魅力・特徴を「コード進行」という点から紐解いていきましょう。
「シンプル」に徹したコード進行が多いSyrup 16gの曲
Syrup 16gのコード進行の特徴としてまず言えるのが、「シンプルな進行が多い」という点です。
洋楽に影響を強く受けたオルタナティブロックでは、J-POPほどコード進行が目まぐるしく変わらない曲が多くなっていますが、Syrup 16gの曲は、そんな邦楽オルタナの特徴をより色濃く反映しています。
実際に、その例を見ていきましょう。
Syrup 16g「生活」コード進行

まず聴いていきたいのは、Syrup 16gの代表曲「生活」です。
疾走感とどこか憂いのある空気感が印象的なこの曲のコード進行は、
G♭→A♭→B♭m(→D♭)
のくり返しがメインになっています。
曲のほとんどがこの進行で、サビで
D♭/G♭→A♭→B♭m(→D♭)
になる、という、全編を通してシンプルな進行でできているのが特徴です。
Syrup 16g「Sonic Disorder」コード進行

こちらも彼らの代表曲「Sonic Disorder」。
そのコード進行は、
Cm→A♭→(B♭sus4)→B♭
のくり返しでほとんど進んでいきます。
サビになるとその進行は
A♭maj7→E♭maj7
のくり返しに変わり、さらにシンプルになっています。
この2曲のコード進行を見ても、Syrup 16gの曲展開がストレートでシンプルに仕上がっていることが分かります。
そんなコード使いこそが、いい意味で武骨なバンドのサウンドを作り上げているのではないでしょうか。
意外にも明るいコード進行が多いSyrup 16g
また、メジャーやメジャー7thなど、明るめの響きを使った進行が多いのもSyrup 16gの曲の特徴です。
暗い世界観で知られるバンドなので、意外に思われた方も多いのではないでしょうか。
サウンド全体で見てもアップテンポで疾走感のある曲が多くなっていて、ロックバンドとしての熱量と、多くの人に受け入れられる音楽としてのキャッチーさも持ち合わせていることが分かります。
楽曲の雰囲気の暗さ、内向性といった要素に、コード進行の明るさはそれほど直結していないと言えますね。
「歌詞」の世界観で形作られるSyrup 16gの世界観

シンプルでアップテンポで、決してマイナー調ではないコード進行が特徴のSyrup 16g。
では、そのほの暗い世界観を形作っている一番の要素は何か、と考えると、やはり「歌詞」という答えが出るのではないでしょうか。
ネガティブで後ろ向きで、その中に救いを見せるわけでもない。
そんな「絶望的」と言えるほどの暗さを見せることもある詞世界こそが、彼らの音楽の根幹を支えているのでしょう。
キャッチーなコード進行と、確固たる闇を抱えた歌詞の2つが組み合わさることで、独特の世界観が生み出されていると言えます。
以上、コード進行から見たSyrup 16gの特徴・魅力をまとめてみました。
複雑な進行を用いず、シンプルに仕上がっていることで、コピーをすることも比較的簡単なので、ギター初心者でも、実際に弾いてみることにそれほど苦労はしないでしょう。
進行に表れている彼らの個性を感じながら、改めてその音楽の世界観に触れてみましょう。